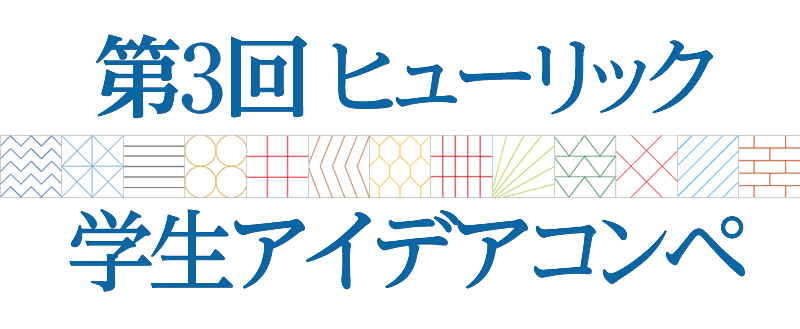
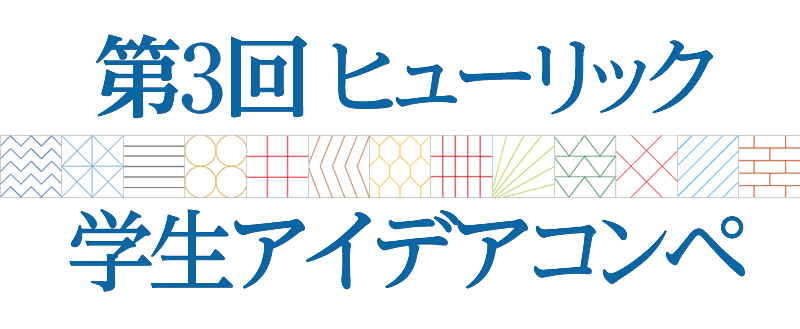

伊香賀 俊治 審査委員
毎回このコンペには、そのアイデアの独自性と現実性の両立が求められてきたが、3回目を迎え、入選にはプラスαの発想が必要になってきているように思う。今回、高い評価を受けた作品のいくつかは、技術の進歩やマーケットの変化が激しい現代社会の中で、建築のサスティナビリティに対して、横浜という立地を利用した、あえて逆説的なソリューションを提案していたように思う。最優秀となった「Yoko Hama Hub」は、都市の流通、インフラと一体となって24時間機能する、まさにハブのような建築であり、また、優秀賞の「YOKOHAMA KALEIDOSCOPE」は、大型映像という現代の技術と建築とをコラボレーションさせ、表情を変えることで存続する建築であった。

亀井 忠夫 審査委員
「Yoko Hama Hub」は、スケールの異なる3つの骨組み、車路による空間の連続性、フードトラックやコンテナ車両の出入による空間の可変性により、現実的プログラムで空間のダイナミズムを創りだしている。「埠頭のストア」については、3枚の床による大きな構成をさらにフィーチャーした形態とした方が、コンセプトがより明快に伝わったと思う。「YOKOHAMA KALEIDOSCOPE」は、時間やシーンによってその姿が可変するように建築と映像がインテグレートされた、構成の美しい提案であるが、さらに大きな都市スケールでの見え方の検証が欲しかった。開放的かつ連続的な空間構成が魅力となっている「文化の風物市」は、実際の使われ方を考慮すると構成がやや変わるのではないかと感じた。

根本 祐二 審査委員
現代港湾はのんびりしていない。東京湾を走る客船、コンテナ船、自動車専用船は驚くほど巨大な構造物であり、さながら、ホテルや物流倉庫や立体駐車場が都市空間の中で顧客のところまで出向いていくようだ。今回、港に面する特徴的な立地を通じて、私が個人的に期待したのは、静止構造物を描くことに慣れた設計者が、いかに現代港湾の動きを表現してくれるかであった。
2次審査に残った提案の多くは港の特徴を強く意識していたが、特に、「ヨコハマハブ」、「文化の風物市」、「ワールドヨコハマ」は、現代港湾のダイナミズムを都市に取り入れようとそれぞれに工夫した楽しい提案だった。難しい課題に答えを出したすべての参加者に心から敬意を表したい。

畠中 克弘 審査委員
今回のテーマは「ビジット・ヨコハマ」。横浜を訪れた人々を呼び込む施設、横浜へ人々を呼び込む施設の提案が求められた。ある意味で、建築を都市とどう関係づけるか、その関係のデザインが問われたコンペだったといえる。「Yoko Hama Hub」は、フードトラックやイベントコンテナを都市に送り出す拠点となる機能を建築に持たせることで、建築の内外に活力を与えることが意図されていた。「文化の風物市」は、与えられた敷地からあえて逸脱して周囲の公園や建築とブリッジで結び、スロープによるひとつながりの内部空間に人々を呼び込むデザインとなっていた。いずれも、建築で営まれるアクティビティを周囲へ放出しながら、人々を建築にいざなう魅力をいかにつくるかが練られている。内向きに小さくまとまるのでなく、外向きにはみ出そうとする志向に好感を持った。

西浦 三郎 審査委員
今回の学生アイデアコンペは、ヒューリックの注力分野の一つである「観光」をテーマにし、敷地を「横浜」に設定しました。今回も審査を楽しみにしていましたが、作品のレベルの高さや、学生さんたちの熱の入ったプレゼンテーションは予想以上でした。個人的には、最優秀作に選ばれた「Yoko Hama Hub」そして優秀作に選ばれた「YOKOHAMA KALEIDOSCOPE」と「埠頭のストア」に一票を投じました。いずれも発想のユニークさと実現性を両立した作品でしたが、なかでも最優秀作のチームの用意周到な準備と検証によるプレゼンテーションは、我々の仕事にも通じるところだと感心しました。コンペを始め3回目を迎えましたが、確実に年々レベルが高くなっていると感じています。第4回も多くの学生の皆さんの参加をお待ちしています。
主催:ヒューリック株式会社
後援:日経アーキテクチュア





隈 研吾 審査委員長
ヒューリックのコンペでは、学生を対象としているけれども、単なるアイデアコンペではなく、リアルでプラクティカルであることが求められていることがユニークであり、昨今の建築をめぐる状況の中でも意味があるコンペだと高い評価を獲得している。
しかし、リアルでプラクティカルであるだけでは、このコンペに勝つことができないということを、今回の結果は教えてくれる。一等案は、都市の中の一般的な商業建築に対する一種の挑戦であった。そこで提案されているのは、単なる美しくかっこのいいテナントビルではなく、都市の流通システム、インフラ自体に対する異議申し立てであり、批評であり、挑戦であった。そこで提示された問題の根はとても深く、都市とは何か、商業とは何かというところにまで、届いている。
読む人が読み、見る人が見れば、この案がいかに現代の都市に対して挑戦的であり、深い視点をもっているかが分かるのである。そして同時に、それが実際の商業施設としても、楽しそうで、「行ってみたいな!」と思わせるところが、この案のミソなのである。
一言でいえば、リアリティとクリティシズムが両立しているのである。そのようなものこそが、本当のリアリティであり、本当のクリティシズムだということを、この案はわれわれに教えてくれるのである。